こんにちは、元MSのヒサシです。
令和以降、医薬品卸のMSは“自主回収”“出荷停止”“出荷調整”と呼ばれる現象によって苦しんでいます。
しかしながら、これらの出来事に付随して発生する業務。
現役のMS以外には、イマイチ実態が掴みにくい側面もあります。
とりわけ出荷調整については、顧客の知らないところでMSが凄まじい負荷に晒されています。
そこで今回は『医薬品の出荷調整または出荷停止の際、医薬品卸のMSがどういった仕事をしているのか?』という事について記事化してみました。
さて、この記事を書いているのは2020年の12月下旬ですが…
業界内では【イトラコナゾール錠の自主回収問題】が炎上する一方です。
健康被害の元凶となったイトラコナゾール錠そのものだけでなく、製造メーカーである小林化工の他品目までもが問題アリと行政から指摘されています。
さらには、小林化工と関係のあるメーカーの医薬品までも出荷調整、あるいは出荷停止となりつつあります。
こういった場合、医薬品卸のMSにとっては多忙を極める展開となります。
問題品の自主回収に始まり、代替品の手配、そして出荷調整の状況を加味した上での按分作業。
MSの名誉のために書かせていただきますが、これら一連の業務は決して楽なものではありません。

…というか、ぶっちゃけ辛いです!!
では、それはなぜなのか?
MSにとっては1円の実績にもならない業務だからです!!
そのくせ、出荷調整絡みの仕事をいくらこなしたからといって、上司(会社)から褒められることなどありません。
付け加えると、医療機関からは出荷調整となったことについて理不尽なクレームを叩き付けられたり、代替品の状況についてせっつかれたり、とにかくストレスが半端じゃないです。
そういったクレーム対応を含めて、MSならばやって当たり前。
どんなに嫌でも、どんなに憂鬱でも、MSとしてやり遂げないといけない。
それがMSにとっての“出荷調整に付随する業務”なのです。
製薬会社の都合による自主回収によって医薬品卸のMSは苦しんでいる!
自主回収時にセットで発生する忌々しい現象。
即ち、出荷調整&出荷停止によって、今日もどこかでMSが苦しんでいます。
まさに、MSの心身を蝕むバッドイベントです。
その辺りの事情について、MS時代の体験談を交えて語っていきます!
売れっ子MSほど苦しむ自主回収

MSとして売れている人ほど、多くの施設で、多くの薬剤を納めています。
MRが頑張ってプロモーションしている新薬から、MRも見向きもしないような長期収載品や後発品まで、本当に様々です。
そんな売れっ子のMSほど苦しむ、最悪のイベント…
それが“自主回収”です!!
なぜ売れっ子MSが苦しむのかと言うと、これは単純な話です。
売れていないMSより、売れているMSの方が“自主回収の対象薬”を納めている可能性が高いからです。
例えば、高シェア先を5軒担当しているMSと、10軒担当しているMSがいたとします。
この場合、当然ながら後者の方が、自主回収のために多くの時間と労力を割く必要に迫られます。
ちなみにですが、まだ私がMSだった頃、営業所のエースMSが自主回収関連の業務に追われ、マジで廃人になりかけている場面を見かけたことがあります。

しかも、それは一度や二度ではありませんでした(汗)
製薬会社の都合によって、売れているMSほど苦しむ。
これがMSという職業の理不尽なところです。
ですが、MSにとって本当の地獄はここからです。
この自主回収に伴って、その後は高確率で出荷調整・出荷停止が発生します。
この『自主回収』⇒『出荷調整&出荷停止』の悪しきコンボによって、多くのMSが苦しんでいます。
MSにとって煩わしい代替品の手配業務

そもそも、出荷調整・出荷停止とは何なのか?
その点について、ひとまず解説させて下さい。
例えばですが、A社が販売しているA薬、B社が販売しているB薬、2種類の薬剤が市場にあるとします。
さらに、これら2種類の薬剤は同種同効品であり、市場におけるシェアは同じくらいだとします。
さて、そんな状況でA薬について問題が指摘され、一部のロットのものが自主回収になったと仮定します。
その後、A薬の他のロットにも欠陥が見付かり、ついにはA薬それ自体の出荷(供給)がストップします。
これが『出荷停止』と呼ばれる現象です。
(※出荷停止について、具体例としては本記事の冒頭で紹介した【小林化工のイトラコナゾール錠】が該当します。)
この場合、MSは代替品としてB社が販売しているB薬を納品する必要が出てきます。
しかし、市場にB薬を安定供給するに当たって、B社の製造能力にも限界があります。
つまり、元々B薬を使用している施設に加えて、少し前までA薬を使用していた施設にまでB薬を供給するだけの余裕が無いのです。
つまり、B社目線だと需要が大きすぎて供給が追い付かない状況というワケですね。
そこで発生する現象が『出荷調整』です。
こういった状況では、B社は元からB薬を使っている施設への供給を優先します。
自社医薬品のユーザーを優先するのは、B社(=メーカー)として当然のことです。
仮にですが、B社におけるB剤の市場への供給量を100としましょう。
その場合、B社と医薬品卸との間では、こんな会話が展開されています。

いかがでしょうか?
あくまで一例ですが、製薬会社と医薬品卸の間にて起こる出荷調整とは、大体こんなイメージです。
…で、結局のところA薬の使用施設に頭を下げるのは、MSが行うという流れになります。

全く、損な役回であると言う他ありません…(汗)
当然、A社のMRもA薬が自主回収になった時点で、各施設に謝罪行脚はしています。
ですが、代替品を用意できないという意味で、MSはメーカーとは別のベクトルで取引先から怒られるのです。
あるいは、代替品を何としてでも用意しろと要求されます。
どちらにせよ、MSにとっては凄まじいストレスです。
元MSとして断言しますが、コレは本当にしんどいです。
顧客と会話する度に、メンタルがガッツリと削られますので。(汗)
例えばですが、出荷調整時にMSが強いられる会話とは下記のような感じです。

いかがでしょうか?
MSの立場からすれば、無理ゲーもいいところです。
実はこれ、私がMSだった頃の実体験です。
一字一句その通りではありませんが、大体こんな感じのことを言われました。
これは出荷停止・出荷調整に限ったことではありませんが…
注文を減らす、あるいは取引自体をストップすることをチラつかせる【厄介な取引先】だったんですよね。(汗)
(※理不尽すぎる反面、自社のシェアが結構高かったことから、結局のところMSとしては彼らの要求を吞むことが多かったです。)
ここで紹介した会話はあくまで一例ですが、タチの悪い取引先はMSに容赦なく無理難題を押し付けてきます。
または、代替品のことだけでなく、ここでいうA薬が自主回収(出荷停止)になったことについて、その不満をなぜかMSにぶつけてきたりもします。
例えば『A薬が出荷停止!?ふざけるなよ!どうしてくれるんだ!?』とかね。
そんなことはMSではなく、A社のMRに言えって感じですよね。
でも、なぜかMSはスケープゴート的な役回りになるんですよ。

この理不尽さは、MS経験者にしか理解できないかと…
一言でまとめると、あくまで一部の医療従事者だけですが、薬の供給云々について文句を言いたいだけなんですよね。
それも、MSよりも立場が強いことを盾にして…です。
ハッキリ言ってクソです。
顧客だろうが何だろうが、人間的には誉められたモノではありません。
しかし、いくらクソな取引先であっても、MSにとっては“お客様”であるのも事実です。
よって、いくら不満のはけ口にされようとも、MSは取引先からの要求に応え、彼らのために尽力する義務があります。
だから辛いのです!!!
まとめ:出荷調整の際、MSは陰で凄まじい業務量をこなしている!

MR目線だと中々分かりにくいところですが、出荷停止・出荷調整のときのMSの業務量は凄まじいものがあります。
在庫状況を勘案して、各取引先に代替品を上手く割り振るなど、色々な意味でバランス感覚が求められます。
その結果、社内にて代替品の割り振り方を巡って、MS同士でのバトルに発展することも少なくないです。
その中でも、特に皺寄せを受けるのが売れっ子のMSです。
繰り返しになりますが、自主回収の対象薬を納めていた担当施設が多いMSほど地獄を味わいます。
その上、代替品の手配についても時間と労力を割く羽目になります。
これは誇張でも何でもなく、純然たる事実です。
製薬会社から自主回収の告知が出たとき、MSは自社から納めた自主回収対象のロット品を回収すれば良い。
そのような単純な話では決してありません。
代替品の手配・納品なども行うこともまた、MSにとっては大切な業務なのです。
これら一連の仕事はMSにとってストレスであり、心身共に疲弊する要因でもあります。
場合によっては【出荷調整によってMSとMRと不仲になる】こともありますので。
こういった人間関係的なストレスもまた、MSにとっては軽視できない要素なんですよね。
この辺りが【MSは激務である】と言われる理由の1つでもあります。
とにかく、最後に言いたいことは…

全国のMSよ、頑張れ!!
…ということです。(汗)
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

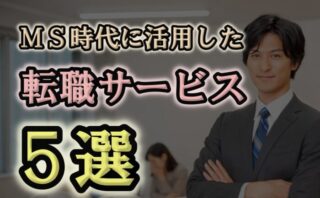
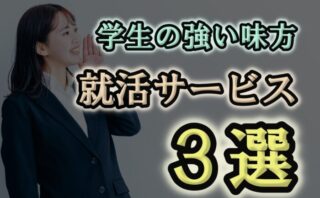
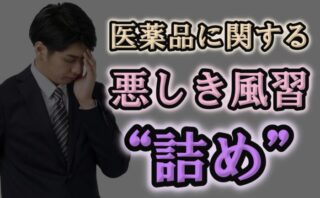
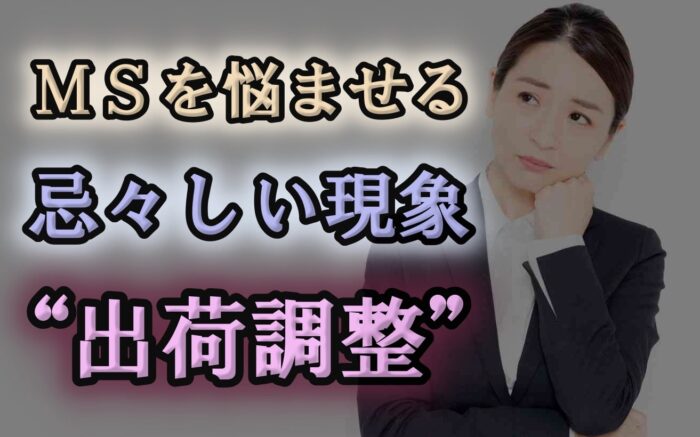
コメント投稿はこちら